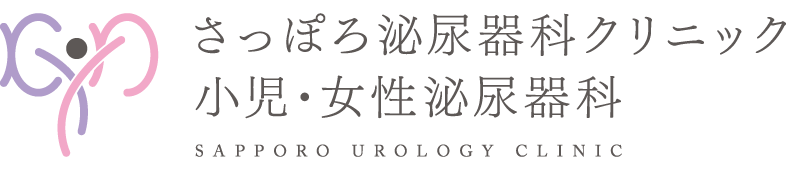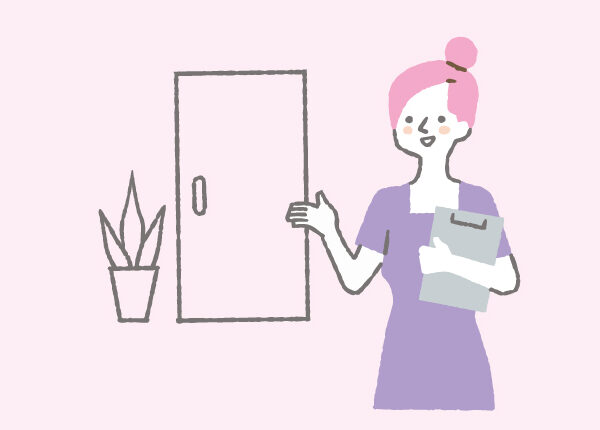「最近、体に違和感がある」「パートナーが性病かもしれない」——そんな不安を感じていませんか?
性病(性感染症、STD)は誰でも感染する可能性がある病気で、日本では年間100万人以上が感染していると推定されています。
恥ずかしさから受診をためらう方も多いですが、早期発見・早期治療でほとんどの性病は完治可能です。
ここでは泌尿器科専門医が、性病の種類・症状・検査・治療・予防法を正確かつわかりやすく解説します。
【1. 性病(STD・STI)とは?】
性病は正式には**性感染症(Sexually Transmitted Infections / Diseases)**と呼ばれ、性的接触によって感染する病気の総称です。
- 原因:細菌、ウイルス、原虫など
- 感染経路:膣性交・オーラルセックス・アナルセックス
- 無症状のまま感染している人も多い
【2. 主な性病の種類と特徴】
| 性病名 | 原因 | 主な症状 |
| クラミジア感染症 | クラミジア菌 | 男性:排尿痛・膿 / 女性:おりもの異常、不妊の原因 |
| 淋病 | 淋菌 | 強い排尿痛と膿。女性は軽症で見逃されやすい |
| 梅毒 | 梅毒トレポネーマ | 無痛のしこり、放置で全身症状 |
| マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症 | Mycoplasma genitalium | 男性:軽い排尿痛・少量の分泌物 / 女性:おりもの異常・下腹部痛。不妊や流産の原因にも |
| 性器ヘルペス | 単純ヘルペスウイルス | 性器の水ぶくれ、再発あり |
| 尖圭コンジローマ | HPV | 性器にイボ。がんの原因となる型も |
マイコプラズマ・ジェニタリウムとは?
近年注目されている比較的新しい性感染症で、1980年代に発見されました。
症状はクラミジアや淋病と似ていますが、非常に薬剤耐性化が進んでいるのが特徴です。
- 感染経路:膣性交、アナルセックス、オーラルセックス
- 潜伏期間:1~3週間程度
- 男性の症状:軽度の排尿痛、透明~白色の少量の分泌物、無症状も多い
- 女性の症状:おりもの異常、軽い下腹部痛、骨盤内炎症性疾患(PID)、不妊や流産リスク
- 治療の難しさ:マクロライド系(アジスロマイシン)やキノロン系(ミノサイクリン、モキシフロキサシン)に耐性を持つ株が増加
- 検査:遺伝子検査(NAAT法)が必要。通常のクラミジア・淋病検査では検出不可
注意:国内でも耐性菌が急増しており、自己判断での市販薬使用は無効な場合が多いです。必ず医療機関で検査と薬剤感受性に基づいた治療を受けてください。
【3. 性病の主な感染経路】
- 膣性交:コンドームなしは高リスク
- オーラルセックス:のどのクラミジア・淋病・マイコプラズマ感染
- アナルセックス:直腸感染リスクが高い
- 接触感染(まれ):タオル・下着共有
- 血液感染:梅毒、B型肝炎 など
【4. 性病の症状チェック】
男性のよくある症状
- 排尿時の痛み・しみる感覚
- 膿や透明な分泌物
- 性器の発疹・しこり
- 精巣の腫れや痛み
女性のよくある症状
- おりものの量・色・匂いの変化
- 外陰部のかゆみや痛み
- 不正出血、下腹部痛
- 不妊や流産の原因になることも
【5. 性病の検査方法と時期】
- 尿検査:クラミジア、淋病
- 血液検査:梅毒、HIV、B型肝炎
- 遺伝子検査(NAAT):マイコプラズマ・ジェニタリウム、クラミジア、淋病
- 分泌物検査:尿道・膣・子宮頸部
- のどの検査:オーラル感染確認
検査可能な目安
- クラミジア・淋病・マイコプラズマ:感染2~3日後~
- 梅毒:4週間後~
- HIV:3か月後~
【6. 性病の治療法】
- 細菌性(クラミジア・淋病・梅毒・マイコプラズマ):抗生物質で治療。ただしマイコプラズマは耐性株多く、薬剤選択に注意
- ウイルス性(ヘルペス・HPV):再発抑制・症状軽減が中心
治療中の注意
- 薬は必ず最後まで服用
- 完治までは性行為禁止
- パートナーも必ず同時に検査・治療
- 再検査で治癒確認
【7. 性病を予防する5つの方法】
- コンドームを正しく使う(最初から最後まで装着)
- パートナーを限定する
- 定期的な性病検査(年1~2回)
- 性器を清潔に保つ
- ワクチン接種(B型肝炎、HPV)
【まとめ】
性病は、予防でき、早期治療でほぼ完治可能な病気です。
特にマイコプラズマ・ジェニタリウムは発見が遅れると耐性菌治療が困難になるため、軽い症状でも早期検査が重要です。
症状がある場合はもちろん、心配な行為があったらすぐに医療機関を受診しましょう。
恥ずかしがらず、自分と大切な人の健康を守るために行動することが大切です。