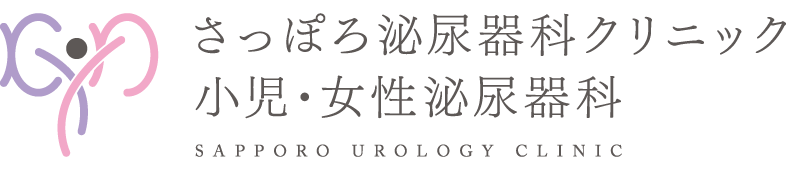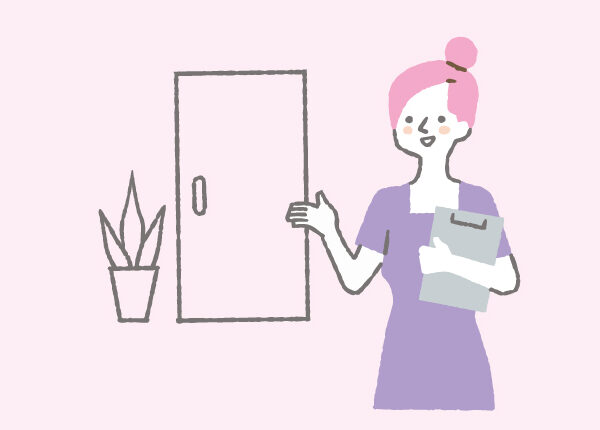【停留精巣について知っておきたいこと】
健診で「停留精巣」と言われ、不安を感じる保護者の方は少なくありません。
停留精巣は男の子に比較的よく見られる病気ですが、適切な時期に治療すれば将来への影響を最小限にできます。ここでは、小児泌尿器科医の立場から、原因・診断・手術・将来の注意点をやさしくまとめます。
【停留精巣とは?】
- 定義:精巣が本来の位置である**陰嚢(いんのう)**におりていない状態。
- 発生の流れ:精巣は胎児期にお腹で作られ、妊娠後期に鼠径部(そけいぶ)を通って陰嚢へ下降します。
- 分類:鼠径部で止まるもの(最多)/お腹の中にある腹腔内停留/経路から逸れる異所性精巣。
- 触知の有無:手で触れられる触知可能精巣と、触れない非触知精巣で方針が変わります。
まぎらわしい状態:移動性精巣(retractile)
普段は陰嚢にあるが、寒さや緊張で一時的に上へ引かれて触れにくくなる状態。治療は不要で、年1回程度の観察が安心です。後年に本当に上がった状態(上昇精巣/獲得性停留)へ移行することがあるため注意します。
【頻度と自然経過】
- 満期産で約3~4%、早産では**20~30%**にみられます。
- 生後3か月頃までは自然下降が多く、6か月を過ぎると自然におりる可能性は低下します(早産児は修正月齢で評価)。
- 片側が約80%、両側が約**20%**です。
【なぜ起こる?】
完全には解明されていませんが、
- 精巣を引き下げる精巣導帯の発達不良
- 胎内でのホルモンバランスの未熟さ
- 胎内環境や遺伝的素因
などが関与すると考えられています。
【診断はどうする?】
- 触診が基本:温かい環境でリラックスした状態を保ち、陰嚢~鼠径部を丁寧に診ます。
- 画像検査の位置づけ:触れない場合でも超音波の有用性は限定的。非触知精巣では腹腔鏡が診断と治療を兼ねた標準的アプローチです。
- 要注意のサイン:
- 両側とも触れない新生児(内分泌疾患の鑑別が急ぎ必要)
- 尿道下裂を合併している場合(性分化疾患の精査を優先)
【なぜ手術が必要?】
- 造精機能の保護:精巣は体温より2~3℃低い環境で最もよく働きます。陰嚢外にある期間が長いほど将来の精子形成に不利です。
- 精巣がんのリスク:一般より約2~8倍高くなります。陰嚢内に固定することで自己触診が可能となり、早期発見につながります。
- 鼠径ヘルニア・捻転の合併、外傷リスクや見た目の問題の改善も期待できます。
【手術の最適時期と方法(精巣固定術)】
いつ手術する?
- 生後6か月(修正)を過ぎても陰嚢内にない場合、6~12か月(遅くとも18か月)までの手術が推奨されます。
- 「もう少し様子を見れば下がるかも」は6か月以降では期待しにくいため、先送りしないことが大切です。
手術の内容
- 手術名:精巣固定術(orchiopexy)。
- 鼠径部の小切開で精巣・精索を丁寧に剥離し、陰嚢内のポケットへ固定します。
- 腹腔内停留では腹腔鏡手術が標準。血管の長さが足りない場合はFowler–Stephens 法(1期/2期)を選択します。
- 合併する鼠径ヘルニアがあれば同時に修復します。
入院と経過
- 施設により日帰り~1泊が一般的。
- 片側30~60分程度、成功率90%以上。主な合併症は**再上昇2~10%、精巣萎縮1~5%**など。
- 入浴は創部の状態により約1週間目から、走跳動作は2~3週間控えます。
将来への影響とフォロー
- 片側で早期手術なら将来の妊よう性は概ね良好。
- 両側や治療が遅れた場合は、妊よう性低下リスクが上がるため、思春期~成人期に必要に応じて精液検査を行います。
- 精巣がんは早期発見が鍵。思春期以降は月1回の自己触診(入浴時にしこり・硬結・左右差を確認)を習慣に。
- 術後は年1回程度の定期診察で、位置の安定・再上昇の有無・反対側の状態をチェックします。
【受診の目安】
- 生後6か月(修正)を過ぎても片側/両側が陰嚢にない
- 両側が触れない、陰茎が小さい、尿道下裂がある(早期精査が必要)
- 以前は降りていたのに、最近触れにくい/上に上がる(上昇精巣の可能性)
- 急な痛み・腫れ(捻転は緊急)
【よくある質問】
Q. 薬や注射で治せますか?
A. 現在の標準治療は**手術(精巣固定術)**です。最適時期に安全に行うことが将来のために重要です。
Q. 手術は痛くないですか?
A. 全身麻酔で実施し、術後は年齢に応じた鎮痛でコントロールします。多くのお子さんが翌日には普段通り動けます。
Q. 反対側も将来上がることはありますか?
A. 上昇精巣は一定割合で起こるため、年1回の診察で確認しましょう。
【まとめ】
停留精巣は6~12(遅くとも18)か月までの早期手術が推奨される病気です。
適切な時期の精巣固定術で妊よう性を守り、自己触診によるがんの早期発見にもつながります。疑わしい場合や不安があれば、先延ばしにせずご相談ください。