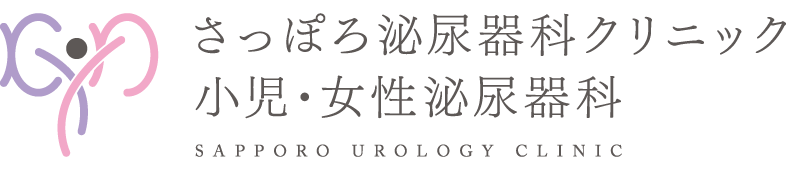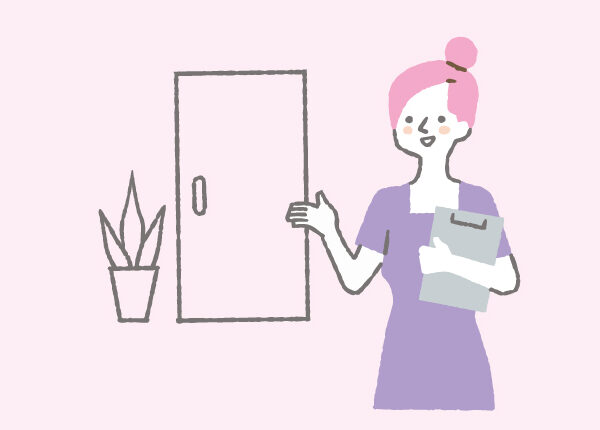【おねしょはいつまで続く?小児泌尿器科医が教える原因と対処法】
お子さんのおねしょでお困りではありませんか。
夜中のシーツ替えや、落ち込むお子さんを前に「何とかしてあげたい」と思うのは当然です。
おねしょは医学的には「夜尿症」と呼び、5歳を過ぎて月1回以上の夜間の失禁がある状態を指します。多くのお子さんが経験する発達過程の一部で、叱って治るものではありません。正しい理解と対応で、しっかり改善が期待できます。
- 5歳の約15~20%、10歳でも約5%にみられます。
- 自然治癒は**年間およそ10~15%**ずつ進みます。
- 専門的な治療を併用すると、改善はぐっと早まります。
【おねしょの原因を知ろう:年齢別の発達とメカニズム】
まず大切なのは、おねしょは怠けや甘えではないこと。背景には次のような要因があります。
乳幼児期(2~4歳)
- 膀胱の容量がまだ小さい
- 膀胱から脳への「いっぱいだよ」の信号が未成熟
- 夜間に尿量を減らす抗利尿ホルモンの分泌が不安定
この時期は発達の範囲内です。焦らず見守りましょう。
学童期(5~7歳)
- 夜間の尿量が多い(夜間多尿):抗利尿ホルモン分泌がまだ弱い
- 膀胱の機能的容量が小さい
- 深い眠りで目覚めにくい体質
これらが単独または重なって起こります。
年長児(8歳以上)
- 体質に加え、便秘や睡眠時無呼吸(いびき·無呼吸)、心理的ストレスなどが関与することも
- まれに糖尿病や腎·尿路の病気が隠れる場合があるため、専門医の評価がおすすめです。
- 家族歴(親も夜尿が長引いた)があると起こりやすくなります。
医学的には、日中症状のない「単一症候性の夜尿症」と、日中の頻尿·尿意切迫·尿漏れなどを伴う「非単一症候性の夜尿症」に分け、対処が少し変わります。
【家庭でできる効果的な対策:今日から始める5つの工夫】
1. 水分摂取のタイミング調整
- 日中はしっかり飲み、夕食以降は控えめに
- 就寝2時間前からは少量ずつに(極端な制限はNG)
- 夕方以降のカフェイン飲料(濃いお茶·コーラ等)は避ける
2. 排尿リズムづくり
- 日中は2~3時間おきにトイレへ
- 就寝直前に必ず排尿、可能なら“ダブルボイド”(寝る直前+布団に入る前)
- 朝起きたらまずトイレへ
3. 便秘対策
- 便秘は膀胱を圧迫し、夜尿を悪化させます
- 毎日同じ時間の排便習慣、食物繊維と十分な日中水分、運動を
4. 睡眠環境の整備
- 就寝·起床時刻を一定に
- いびきや無呼吸があれば耳鼻科や小児科に相談
- トイレまで足元灯で安全に移動できる環境づくり
5. 心理的サポート
- 叱らない·責めないが原則
- できた日はたくさん褒める(シール表・ほめカレンダーが有効)
- 防水シーツや紙おむつは「治療の一部」。お子さんの尊厳に配慮しつつ活用を
やりがちNG:厳しい水分制限、真夜中に親が何度も起こす、罰を与える—いずれも効果が乏しく逆効果になりがちです。
【専門医による治療:行動療法と薬物療法の上手な使い分け】
夜尿アラーム(第一選択の行動療法)
- パンツの湿りをセンサーが感知→音·振動で起こす装置
- 根本改善が期待でき、効果は6~8割。再発率も低め
- 家族の協力が必要。6~8週間で反応を評価し、連続14夜の成功で終了を検討
- 反応が乏しければ設定見直しや他治療へ切替
デスモプレシン(抗利尿ホルモン製剤)
- 夜間尿量を減らす**内服薬(口腔内崩壊錠など)**が標準
- 点鼻製剤は低ナトリウム血症のリスクから夜尿症では推奨されません
- 修学旅行·お泊まり前の短期使用や、夜間多尿が主因のケースで有効
- 服薬時は就寝後の飲水制限を守る(安全のため)
抗コリン薬(膀胱の過活動を抑える)
- 膀胱容量が小さい、日中の尿意切迫·頻尿を伴う場合に検討
- デスモプレシンとの併用で効果が高まることも
その他
- 三環系抗うつ薬(イミプラミン等)は副作用·安全性の観点から原則第3選択。専門医管理下で限定的に
【受診の目安と診療の流れ】
こんなときは受診を
- 5歳を過ぎても週2回以上のおねしょが続く
- 日中の症状(頻尿・尿意切迫・尿漏れ・便秘・繰り返す尿路感染)を伴う
- いびき·無呼吸が強い/口渇·多飲·体重減少がある(糖尿病などの鑑別が必要)
- ご家族もお子さんもつらさが強い
初診で行うこと
- 詳細な問診と排尿·飲水日誌の確認
- 尿検査(糖・蛋白・感染のチェック)
- 必要に応じて腹部診察、便秘評価、超音波検査など
- タイプ別に、**家庭の工夫 → アラーム → 薬(または併用)**の順で提案
【よくある質問】
Q. いつまでに治りますか?
A. 個人差はありますが、**毎年10~15%**ずつ自然に良くなります。治療でさらにスピードアップが期待できます。
Q. 修学旅行が不安です。
A. 事前にご相談ください。デスモプレシンの短期使用や、目立たない吸水パンツ·防水対策で多くのお子さんが安心して参加できます。
Q. オムツは外すべき?
A. 乾いた成功体験を作るため、状況に応じて併用可。お子さんの自尊心に配慮しながら進めましょう。
【まとめ】
おねしょは、多くの子どもにみられる発達上の現象です。
年齢やタイプに合った対策、家庭での地道な工夫、そして必要に応じた専門的治療で、しっかり改善が期待できます。何より大切なのは、叱らず·責めず·褒めて支える姿勢です。
5歳児の約15~20%、10歳でも約5%が経験します。ひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。
当院では、排尿日誌を用いた丁寧な評価、アラーム療法の使い方指導、薬物療法の安全な運用まで、専門医が一貫してサポートします。
追記(院内表記用の注意点)
- デスモプレシン:内服(口腔内崩壊錠)を基本。就寝後は飲水制限を明記
- アラーム:家族同意·実施手順の書面を用意すると継続率が上がります
- 便秘スクリーニング:ブリストル便形状スケール·腹部所見の定型記録
- 耳鼻科連携:いびき·睡眠時無呼吸が疑われる場合の紹介ルートを明示
小児泌尿器科専門医として、上記内容は国内外のガイドラインに整合する一般的推奨に基づき、患者さん向け解説として安全性と正確性を担保しています。必要なら貴院の運用や地域連携先に合わせて文言をさらに最適化します。